
ロッテのあの方については、旧来のファンやコレクターからは
蛇蝎のごとく嫌われているわけですけど、
先日発売の「ご当地ビックリマン」のプロモーションでは
別の方が担当者として応対されていたことから
いよいよ交代かとウワサになっているようです。
実際のところどうなのかは知りませんが、いずれ明らかになるでしょう。
ただ、そう簡単に路線が変わるとは思えないんですよね。
そもそもそれまでの歴代の担当者はいわゆる「ビックリマン世代」で
ファンをメインターゲットにした商品づくりを行ってきたことにより
商品としては閉塞した末期状態に陥っていました。
それに対してあの方…本原氏は「自分が世代ではないこと」を強みとして
外部の目線でブランド戦略に舵をきったことによって
ターゲット層を拡大して商品のV字回復を成し遂げたとされています。
他にも地方創生プロジェクトに代表される
「お菓子以外の方面に対するプロモーション」については、
マイナスの面があったとしてもプラスの面が強調される現状では
現場の声は耳障りのいい謳い文句にかき消されて功績が独り歩きしています。
実際、ウワサレベルで聞かれる負の側面については
裏付けが取れなければ陰謀論的に聞き流されるのも世の常です。
どんな世界でも成果を出した人が強いのは当然の成り行きで、
ロッテ内でこの路線が間違っていないと判断されているうちは
担当者が変わったとしても方向性は変わらないと思われます。
そして私もこのブログを見に来る大半の方も旧来のファン側なので
意見が偏るのはある意味で避けられないことです。
そこで私はAIにこんな調査を依頼してみました。(Gemini Deep Research)
「ビックリマンチョコのコラボ中心の戦略がオールドファンの反発を招いている点や、
投げっぱなしの焼き畑農業と揶揄されていることについて考察してください」
その結果がこちらになります。
ビックリマンコラボ戦略の考察(PDF)
長いので要約するとこんな感じ。
「ビックリマンのコラボ中心の戦略は、ブランドの延命と若年層への購買層拡大というビジネス的成果を上げた一方で、オールドファンからは製品の品質低下や物語性の軽視による反発を招きました。
この批判は、ブランドのコアな価値が短期的な利益のために消費されているという認識から生じたものです。
しかし、企業側の視点では、この戦略はブランドを過去の停滞から脱却させ、新しい「メディア」として再定義し、持続可能な成長を目指す長期的な試みであると解釈できます。」
ブランドとしての成果を重視する企業側と、シールそのものや物語を重視するファン側に
それぞれ言い分があることや、その間に大きな壁があることがきちんと読み取られています。
真に持続可能なブランドを確立するにはファンの信頼を得ることが必要とも分析されていますので、
今後の担当者様にはそういう視点で新たなステージを切り開いていただきたいところです。
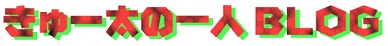


コメント